<アスパラガスは苦い?>
ほんのり甘味があり
やわらかく食べやすく
春の食卓を彩ってくれる
アスパラガス。
でも、
アスパラガスに
「苦み」成分が含まれていることを
ご存知でしょうか?
「苦み」は
春にカラダが必要な成分で
冬に貯めた皮下脂肪や老廃物を
カラダから排出する手伝いをしてくれる
大切な役割を担っています。
今日は、アスパラガスの苦みが
カラダをどう助けてくれるのか
みていきましょう。
<サポニンの苦み>
うど、ふき、ふきのとう、こごみ、木の芽、
タラの芽、つくし、ワラビ、たけのこ、かたくり、
クレソン、せり、ぜんまい、みつば、、、、
春になると「苦み」をもった植物がたくさんでてきます。
「苦み」は植物が外敵から自分の身を守るために
進化の過程で作り出した「毒」です。
なので、「苦み」は人間にとっても毒。
人間の舌にある苦味を感じるセンサー(受容体)は
25種類もあり、これは5味を感じる受容体の中でも
ずば抜けて多いと聞きました。
(ちなみに塩味・酸味は2種類、甘味は1種類、うま味は3種類)
人類は食べ物が毒であるかどうかをいち早く察知できるように
苦み受容体を進化させたようです。
けれども「少量の毒は薬にもなる」
ホメオパシーや予防接種をはじめ
人間はこの毒を薬に変える知恵を持ち合わせています。
「苦み」成分をもつ植物は
人間のカラダから毒を出すため
春のデトックスには欠かせないものとして
昔から重宝されてきました。
さて、この苦み成分は
「サポニン」というもので
植物の根、葉、特に茎の部分に多く含まれています。
確かに、アスパラの茎の部分には苦みがあります。
その他には、
高麗人参・田七人参・お茶・ごぼうの皮や
大豆などのマメ科の植物に多く含まれています。
高野豆腐、大豆、生揚げ、がんも、
油揚げ、おから、豆乳、ゆばなどの
大豆製品として昔から親しまれてきたようです。
サポニンという名前は
水に溶かすと、
石鹸のような泡がでることから
ラテン語の石鹸を意味する
「サポ」からなずけられました。
「天然の界面活性剤」とも呼ばれ、
私たちのカラダの中を綺麗に洗い流してくれています。
サポニンは医学的にも注目されていて
肥満を予防したり、
血流を改善し冷え症をよくし
肝臓を助け解毒を促し
リンパ球を活性化させて免疫力を上げ
血液のサビを止め細胞の老化を防ぐ
など、様々な効果が検証されている成分です。
<アスパラガスの世界>
個人的にはアスパラガスが苦いとは感じたことはありませんが、
確かに、茎の部分、とくにホワイトアスパラガスには
独特の苦みを感じます。
実際、ホワイトアスパラガスの茎の部分に
サポニンが多く含まれているとのこと。
さて、アスパラにもたくさん種類がありますね。
私たちが日本でよく目にするのは
グリーンアスパラガス。

ホワイトアスパラガスも時々見かけますね。

ホワイトアスパラとグリーンアスパラは同じ品種。
土をかぶせて遮光した状態で栽培するため
葉緑素(クロロフィル)がないアスパラができあがります。
あまり日本では見かけませんが
個人的に好きなのは紫アスパラガス

紫アスパラにはカラダの錆びをとる
ポリフェノールのアントシアニンが
グリーンの10倍も含まれていて
さらにビタミンCも糖度も高めです。
FAOによる主要国のアスパラガス生産量の推移を見て見ると
中国が桁違いで1位。メキシコ、アメリカやヨーロッパも順を追って。
日本も多く、10位以内を推移しています。
日本人はアスパラ好きのようです。
<苦みはデトックスを促す>
昔から
「春苦み、夏は酢のもの、秋辛味、冬は油と合点して食え」
と言われるように
春にはカラダが苦みを欲します。
苦みは肝臓の働きを助け
胆のうを刺激し胆汁の分泌を促し
便となって体の老廃物を出す役割を果たします。
冬に貯め込んだ脂肪、古塩や老廃物を
胆のうから出る胆汁でとかし、流す。
苦みを使って私たちは「冬のカラダ」から
「春夏のカラダ」に衣替えをします。
ただ、苦みのあるもは毒でもあるので
時々、少量をこころがけましょう。
また、
食生活を楽しみながら健康を維持、増進には
季節と共生した食生活が大切です。
アスパラガスはもともとは南ヨーロッパ原産。
日本も昔と比べるとずいぶん気候が変わってきましたが、
「身土不二」を考えながら
=その土地の気候風土で育ったものを摂ることが健康にも良いという考え
できるだけ日本でとれた作物から苦みをとることも忘れず。
みなさんの健康を心から祈って。
今日も読んでいただきありがとうございました。
).png?1772250614)



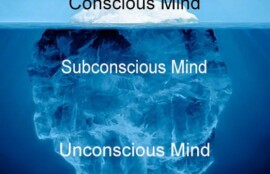


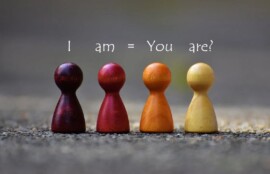
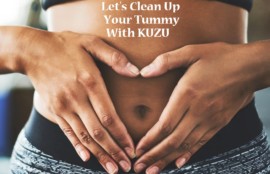


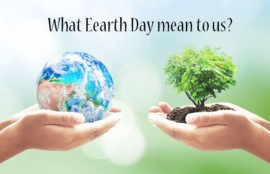


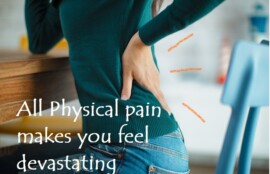

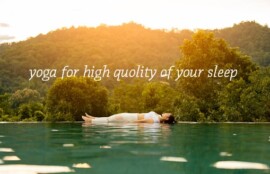



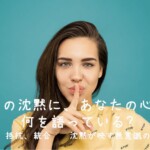


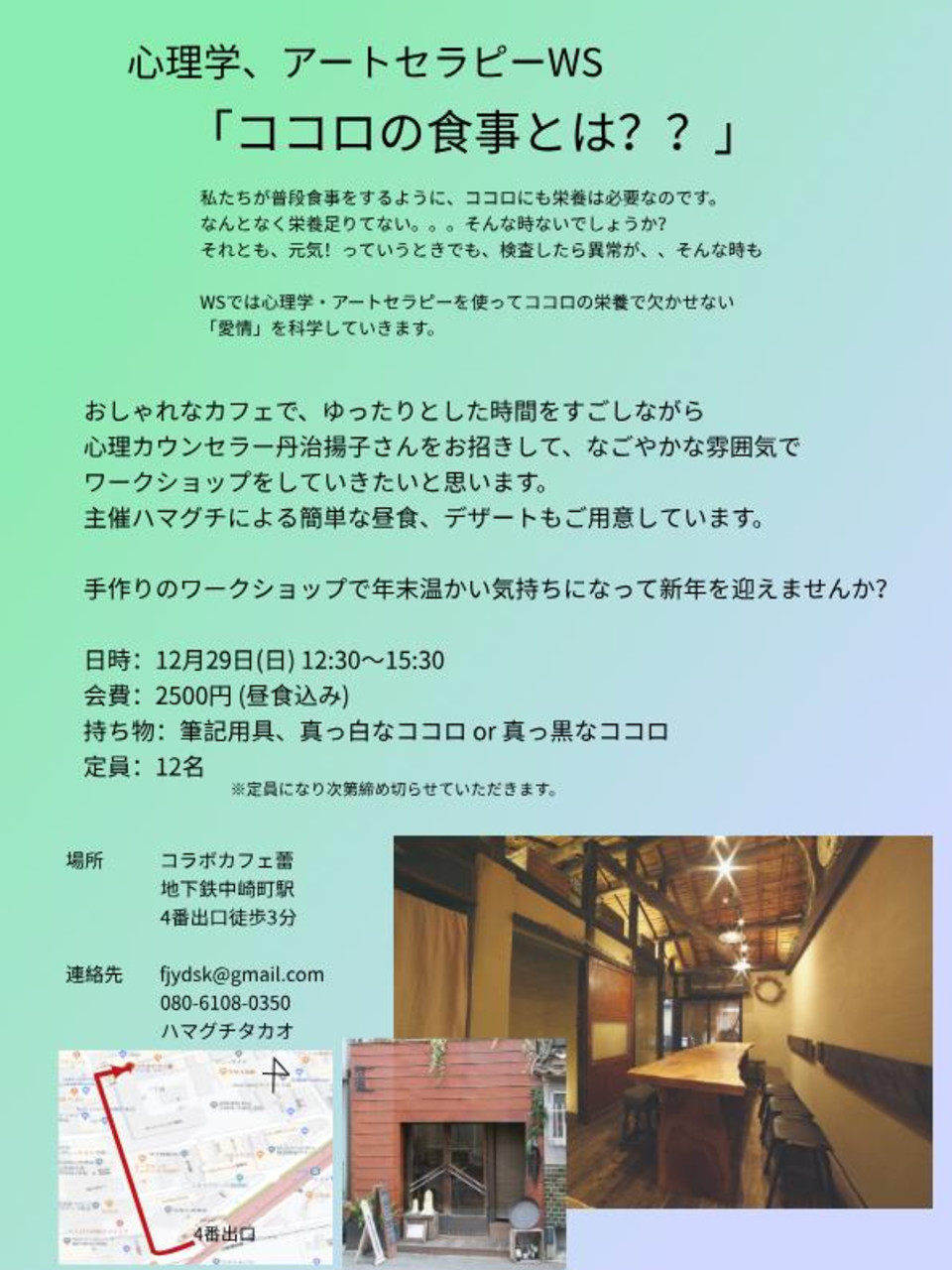
++-pdf.jpg)



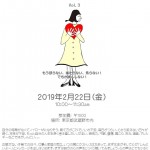

).png?1772250614)